科目別の一覧
- 全ての植物
- サルノコシカケ科
- サルオガセ科
- ヒカゲノカズラ科
- トクサ科
- ウラボシ科
- ソテツ科
- イチョウ科
- マオウ科
- マツ科
- イチイ科
- ヒノキ科
- スイレン科
- ハゴロモモ科
- マツブサ科
- ドクダミ科
- コショウ科
- ウマノスズクサ科
- モクレン科
- バンレイシ科
- クスノキ科
- ショウブ科
- サトイモ科
- オモダカ科
- ヤマノイモ科
- ビャクブ科
- パナマソウ科
- シュロソウ科
- シオデ科
- ユリ科
- イヌサフラン科
- ラン科
- アヤメ科
- ツルボラン科
- ワスレグサ科
- ヒガンバナ科
- キジカクシ科
- ヤシ科
- ミクリ科
- ガマ科
- イネ科
- ツユクサ科
- バショウ科
- ショウガ科
- アケビ科
- ツヅラフジ科
- メギ科
- キンポウゲ科
- ケシ科
- ハス科
- タデ科
- ナデシコ科
- ヒユ科
- ツルムラサキ科
- ビャクダン科
- ボタン科
- ユズリハ科
- ユキノシタ科
- ブドウ科
- フウロウソウ科
- ミソハギ科
- アカバナ科
- フトモモ科
- ハマビシ科
- ニシキギ科
- ヤナギ科
- トケイソウ科
- トウダイグサ科
- オトギリソウ科
- ヒルギ科
- アマ科
- キントラノオ科
- カタバミ科
- マメ科
- ヒメハギ科
- バラ科
- グミ科
- クロウメモドキ科
- アサ科
- クワ科
- イラクサ科
- ウリ科
- ブナ科
- ヤマモモ科
- カバノキ科
- クルミ科
- パパイア科
- アブラナ科
- アオイ科
- ジンチョウゲ科
- ムクロジ科
- ウルシ科
- センダン科
- ミカン科
- ミズキ科
- アジサイ科
- ツバキ科
- カキノキ科
- サクラソウ科
- マタタビ科
- リョウブ科
- ツツジ科
- トチュウ科
- アオキ科
- ムラサキ科
- アカネ科
- リンドウ科
- キョウチクトウ科
- ナス科
- ヒルガオ科
- モクセイ科
- イワタバコ科
- キツネノマゴ科
- ゴマ科
- クマツヅラ科
- ノウゼンカズラ科
- シソ科
- ハマウツボ科
- オオバコ科
- ハナイカダ科
- モチノキ科
- ウコギ科
- セリ科
- トベラ科
- レンプクソウ科
- スイカズラ科
- キキョウ科
- ミツガシワ科
- キク科
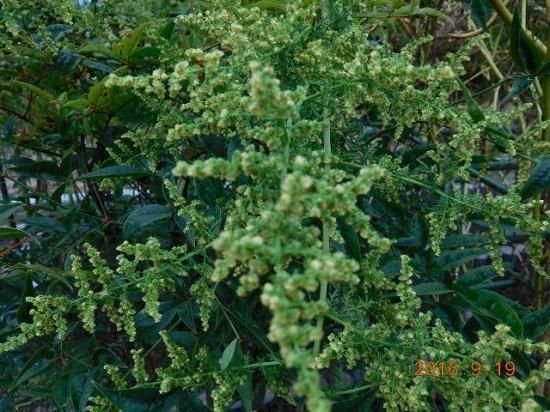


真正双子葉植物Eudicots>中核真正双子葉植物Core Eudicots>キク類Asterids
>キキョウ群Campanulids
キク目Asterales
キク科 Asteraceae ヨモギ属 Artemisia
英名:Sweet Annie、wormwood
生薬名 :オウカコウ(黄花蒿)
利用部分 :全草
利用 :薬用(マラリアの薬 アーテスネートの基源植物)
名前の由来 :独特の臭い(悪臭だといわれる)と葉がニンジンに似ることから
アジア、ヨーロッパにも広く分布し、日本へは中国からの帰化植物。草丈2m近くにも成長し、
今日では道端や、荒地に自生し繁茂している。
晩夏から初秋にかけて黄色い直径1.5mm程の小さな頭状花を穂状につけ、大きな円錐状になる。この様子は他のヨモギの仲間と同じで区別が付きにくいが、葉の様子で鑑別する。葉は3回羽状細裂し、ヨモギの葉とは全く異なる。
名前にもいろいろあるが、もう少しましな名前にならなかったのだろうか?と疑問に思う。
気の毒な名前がついているが、中国では「本草綱目」にすでに収載されている伝統ある薬草。古くから全草を苦味健胃薬に用いていた。全草に香りのもととなる精油が含まれ、精油中には、アルテミシアケトン、カリオフィレン、シネオール、ピネン、カンフェン等の成分が知られている。
近年、この植物からアルテミシニン(artemisinin)が発見され、抗マラリア作用から、マラリアの特効薬発見として2015年、ノーベル生理学・医学賞の対象になり注目を集めた。発見者は中国の女性科学者トゥーユーユー(Tu Youyou)氏。
日本は幸いマラリアの脅威は殆どないが、世界的には多くの人が犠牲になっている感染症の1つ。
従来の薬剤、キニーネやクロロキン製剤に加え、マラリアの特効薬アーテスネート(artesunate)としてアフリカ等で使用されている。
アーテスネートは日本では未承認のため、熱帯病治療薬研究班の保管薬剤の対象にされている。
必要時その使用機関において、保管薬を用いて治療が受けられるようになっている。
参考文献
・朝日百科 世界の植物 (朝日新聞社)
・薬用植物学各論 木村康一・木島正夫共著 (広川書店)
・今日の治療薬 2015 (南江堂)
・植物分類表 大場秀章 編著 (アボック社)