科目別の一覧
- 全ての植物
- サルノコシカケ科
- サルオガセ科
- ヒカゲノカズラ科
- トクサ科
- ウラボシ科
- ソテツ科
- イチョウ科
- マオウ科
- マツ科
- イチイ科
- ヒノキ科
- スイレン科
- ハゴロモモ科
- マツブサ科
- ドクダミ科
- コショウ科
- ウマノスズクサ科
- モクレン科
- バンレイシ科
- クスノキ科
- ショウブ科
- サトイモ科
- オモダカ科
- ヤマノイモ科
- ビャクブ科
- パナマソウ科
- シュロソウ科
- シオデ科
- ユリ科
- イヌサフラン科
- ラン科
- アヤメ科
- ツルボラン科
- ワスレグサ科
- ヒガンバナ科
- キジカクシ科
- ヤシ科
- ミクリ科
- ガマ科
- イネ科
- ツユクサ科
- バショウ科
- ショウガ科
- アケビ科
- ツヅラフジ科
- メギ科
- キンポウゲ科
- ケシ科
- ハス科
- タデ科
- ナデシコ科
- ヒユ科
- ツルムラサキ科
- ビャクダン科
- ボタン科
- ユズリハ科
- ユキノシタ科
- ブドウ科
- フウロウソウ科
- ミソハギ科
- アカバナ科
- フトモモ科
- ハマビシ科
- ニシキギ科
- ヤナギ科
- トケイソウ科
- トウダイグサ科
- オトギリソウ科
- ヒルギ科
- アマ科
- キントラノオ科
- カタバミ科
- マメ科
- ヒメハギ科
- バラ科
- グミ科
- クロウメモドキ科
- アサ科
- クワ科
- イラクサ科
- ウリ科
- ブナ科
- ヤマモモ科
- カバノキ科
- クルミ科
- パパイア科
- アブラナ科
- アオイ科
- ジンチョウゲ科
- ムクロジ科
- ウルシ科
- センダン科
- ミカン科
- ミズキ科
- アジサイ科
- ツバキ科
- カキノキ科
- サクラソウ科
- マタタビ科
- リョウブ科
- ツツジ科
- トチュウ科
- アオキ科
- ムラサキ科
- アカネ科
- リンドウ科
- キョウチクトウ科
- ナス科
- ヒルガオ科
- モクセイ科
- イワタバコ科
- キツネノマゴ科
- ゴマ科
- クマツヅラ科
- ノウゼンカズラ科
- シソ科
- ハマウツボ科
- オオバコ科
- ハナイカダ科
- モチノキ科
- ウコギ科
- セリ科
- トベラ科
- レンプクソウ科
- スイカズラ科
- キキョウ科
- ミツガシワ科
- キク科

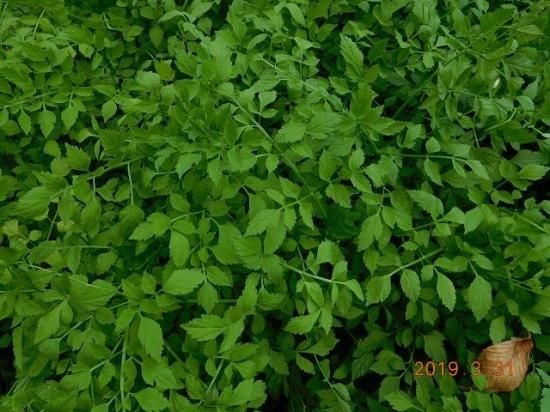
セリ(芹)Oenanthe javanica DC
真正双子葉植物Eudicots>中核真正双子葉植物Core Eudicots>キク類Asterids
>キキョウ群Campanulids
セリ目Apiales
セリ科 Apiaceae セリ属 Oenanthe
春の七草の一つ 緑黄色野菜
生薬名 :スイキン(水芹)
利用部分 :全草 根
用途 :食用、薬用
名前の由来 :せ(競)りあう、せ(競)りだすの意で、群がるように生い出て、摘んで 摘んでも
後から後から競うように生ずるので、この名がある。
水辺や湿地、田の畦などに群生する。春の七草の一種で、軟らかく葉に独特の香りがあり、食用にされる。
地下茎を匍匐枝状に伸ばし、節ごとに新芽を出す、生命力旺盛な多年草。夏7〜8月にかけて白い小さな5弁の花を複散形花序に咲かせる。
欧米ではセリを食用にする習慣はないが日本では古くから七草粥、お浸し、和え物などに利用されてきた。
万葉集にもセリ摘みの様子が詠まれている。
早春の頃が軟らかく香りも強く珍重される。晩春から秋の彼岸頃にかけては成長が良すぎ硬くなり、あくが強くなので、食べるのに適さない。
独特の香りには解熱、解毒作用があると言われている。
抗酸化作用のあるβーカロテンやビタミンCを多く含み、カリウム、貧血を防ぐ鉄なども含む緑黄野菜。栄養価にも優れている。
ー万葉集 セリを詠む和歌 二首ー
「あかねさす昼はたたびてぬばたまの夜の暇に摘める芹これ」(巻20 4455)
「ますらをと思へるものを太刀佩きてかにはの田井に芹ぞ摘みける」(巻20 4456)
セリを摘む様子を詠った和歌。古くからセリが食用にされていたことが分かる。
参考文献
・朝日百科 世界の植物 (朝日新聞社)
・山渓名前図鑑 野草の名前 夏 高橋勝雄著 (山と渓谷社)
・万葉の植物 松田 修著 (保育社)
・山野草ハンドブック 伊沢一男(主婦の友社)
・美味しい山菜 おくやまひさし(文一総合出版)
・食材事典 原田孝子監修(学研)
・新食品成分表 2017年(東京法令出版株式会社)
・植物分類表 大場秀章 編著 (アボック社)