科目別の一覧
- 全ての植物
- サルノコシカケ科
- サルオガセ科
- ヒカゲノカズラ科
- トクサ科
- ウラボシ科
- ソテツ科
- イチョウ科
- マオウ科
- マツ科
- イチイ科
- ヒノキ科
- スイレン科
- ハゴロモモ科
- マツブサ科
- ドクダミ科
- コショウ科
- ウマノスズクサ科
- モクレン科
- バンレイシ科
- クスノキ科
- ショウブ科
- サトイモ科
- オモダカ科
- ヤマノイモ科
- ビャクブ科
- パナマソウ科
- シュロソウ科
- シオデ科
- ユリ科
- イヌサフラン科
- ラン科
- アヤメ科
- ツルボラン科
- ワスレグサ科
- ヒガンバナ科
- キジカクシ科
- ヤシ科
- ミクリ科
- ガマ科
- イネ科
- ツユクサ科
- バショウ科
- ショウガ科
- アケビ科
- ツヅラフジ科
- メギ科
- キンポウゲ科
- ケシ科
- ハス科
- タデ科
- ナデシコ科
- ヒユ科
- ツルムラサキ科
- ビャクダン科
- ボタン科
- ユズリハ科
- ユキノシタ科
- ブドウ科
- フウロウソウ科
- ミソハギ科
- アカバナ科
- フトモモ科
- ハマビシ科
- ニシキギ科
- ヤナギ科
- トケイソウ科
- トウダイグサ科
- オトギリソウ科
- ヒルギ科
- アマ科
- キントラノオ科
- カタバミ科
- マメ科
- ヒメハギ科
- バラ科
- グミ科
- クロウメモドキ科
- アサ科
- クワ科
- イラクサ科
- ウリ科
- ブナ科
- ヤマモモ科
- カバノキ科
- クルミ科
- パパイア科
- アブラナ科
- アオイ科
- ジンチョウゲ科
- ムクロジ科
- ウルシ科
- センダン科
- ミカン科
- ミズキ科
- アジサイ科
- ツバキ科
- カキノキ科
- サクラソウ科
- マタタビ科
- リョウブ科
- ツツジ科
- トチュウ科
- アオキ科
- ムラサキ科
- アカネ科
- リンドウ科
- キョウチクトウ科
- ナス科
- ヒルガオ科
- モクセイ科
- イワタバコ科
- キツネノマゴ科
- ゴマ科
- クマツヅラ科
- ノウゼンカズラ科
- シソ科
- ハマウツボ科
- オオバコ科
- ハナイカダ科
- モチノキ科
- ウコギ科
- セリ科
- トベラ科
- レンプクソウ科
- スイカズラ科
- キキョウ科
- ミツガシワ科
- キク科
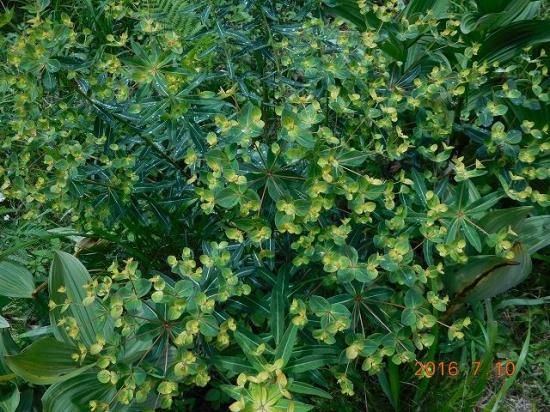


真正双子葉類Eudicots >中核真正双子葉類Core Eudicots >マメ群Fabids
キントラノオ目Malpighiales
トウダイグサ科 Euphorbiaceae トウダイグサ属 Euphorbia
生薬名 :ダイゲキ(大戟)
利用部分 :根
利用 :漢方薬、
名前の由来:上部の葉が黄色に染まりので、昔の明かりを灯もす照明器具の橙台に似るための名。
葉を燈台の皿に、花を橙台の燈芯に見立てた。
本邦各地の山野に自生する多年草。茎は直立し葉や茎を折ると白い乳液が出る。皮膚に付くとかぶれることがある。葉は互生し長さ3〜6cm、幅1〜2cmで長楕円形、茎の先で4〜5枚の葉が輪生する。
輪生する葉の脇から数本の枝が傘状に分岐する。枝先では2枚の総苞葉の間に黄褐色のつぼ型の杯状花序が付く。中に雄しべ、雌しべがある。花のように見えるが、実際は偽花で花に見えるのは4つの楕円形の黄色い蜜を出す器官(腺体)。雌しべが受粉すると、雌しべは外へ伸び出てその先に丸い球形の実をつける。
有毒植物ではあるが漢方では根を利尿薬にする。
因みに学名の属名Euphorbiaは、ローマ時代の医師エウフォルブスに因んで付けられたもの。
彼が始めてこの種の植物の乳液を薬用にしたためという。
歴史のある植物だがアルカロイド、ユーフォルビンなどを含み、有毒なため安易に用いてはならない。
同じ属に属するものには、ナツトウダイ、タカトウダイ、ノウルシなどが知られている。
漢方薬に用いるダイゲキ(大戟)は神農本草経にも収載されている程、古くから用いられてきた生薬だが、古来よりその起源は諸説あり、アカネ科、マメ科、トウダイグサ科などまちまちで、それぞれ異なる科の植物由来をダイゲキ(大戟)と称している。ちなみにトウダイグサ科のダイゲキ(大戟)は京大戟と言われる。
日本産和大戟はトウダイグサの根を乾燥したもの。韓国産ダイゲキ(大戟)はナツトウダイの根を乾燥したものが用いられる。日本産和大戟は現在流通していない。
参考文献
・朝日百科 世界の植物 (朝日新聞社)
・薬用植物学各論 木村康一・木島正夫共著 (広川書店)
・花と樹の事典 木村陽一郎 監修 (柏書房)
・原色和漢薬図鑑 難波恒雄著 (保育社)
・山渓名前図鑑 野草の名前 春 高橋勝雄著 (山と渓谷社)
・山野草ハンドブック 伊沢一男(主婦の友社)
・野草図鑑 夏 (北隆館)
・植物分類表 大場秀章 編著 (アボック社)