科目別の一覧
- 全ての植物
- サルノコシカケ科
- サルオガセ科
- ヒカゲノカズラ科
- トクサ科
- ウラボシ科
- ソテツ科
- イチョウ科
- マオウ科
- マツ科
- イチイ科
- ヒノキ科
- スイレン科
- ハゴロモモ科
- マツブサ科
- ドクダミ科
- コショウ科
- ウマノスズクサ科
- モクレン科
- バンレイシ科
- クスノキ科
- ショウブ科
- サトイモ科
- オモダカ科
- ヤマノイモ科
- ビャクブ科
- パナマソウ科
- シュロソウ科
- シオデ科
- ユリ科
- イヌサフラン科
- ラン科
- アヤメ科
- ツルボラン科
- ワスレグサ科
- ヒガンバナ科
- キジカクシ科
- ヤシ科
- ミクリ科
- ガマ科
- イネ科
- ツユクサ科
- バショウ科
- ショウガ科
- アケビ科
- ツヅラフジ科
- メギ科
- キンポウゲ科
- ケシ科
- ハス科
- タデ科
- ナデシコ科
- ヒユ科
- ツルムラサキ科
- ビャクダン科
- ボタン科
- ユズリハ科
- ユキノシタ科
- ブドウ科
- フウロウソウ科
- ミソハギ科
- アカバナ科
- フトモモ科
- ハマビシ科
- ニシキギ科
- ヤナギ科
- トケイソウ科
- トウダイグサ科
- オトギリソウ科
- ヒルギ科
- アマ科
- キントラノオ科
- カタバミ科
- マメ科
- ヒメハギ科
- バラ科
- グミ科
- クロウメモドキ科
- アサ科
- クワ科
- イラクサ科
- ウリ科
- ブナ科
- ヤマモモ科
- カバノキ科
- クルミ科
- パパイア科
- アブラナ科
- アオイ科
- ジンチョウゲ科
- ムクロジ科
- ウルシ科
- センダン科
- ミカン科
- ミズキ科
- アジサイ科
- ツバキ科
- カキノキ科
- サクラソウ科
- マタタビ科
- リョウブ科
- ツツジ科
- トチュウ科
- アオキ科
- ムラサキ科
- アカネ科
- リンドウ科
- キョウチクトウ科
- ナス科
- ヒルガオ科
- モクセイ科
- イワタバコ科
- キツネノマゴ科
- ゴマ科
- クマツヅラ科
- ノウゼンカズラ科
- シソ科
- ハマウツボ科
- オオバコ科
- ハナイカダ科
- モチノキ科
- ウコギ科
- セリ科
- トベラ科
- レンプクソウ科
- スイカズラ科
- キキョウ科
- ミツガシワ科
- キク科
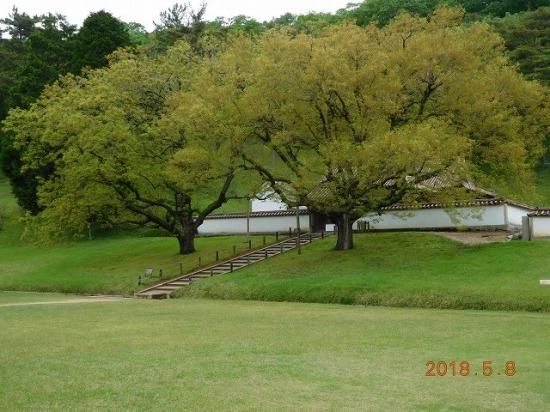
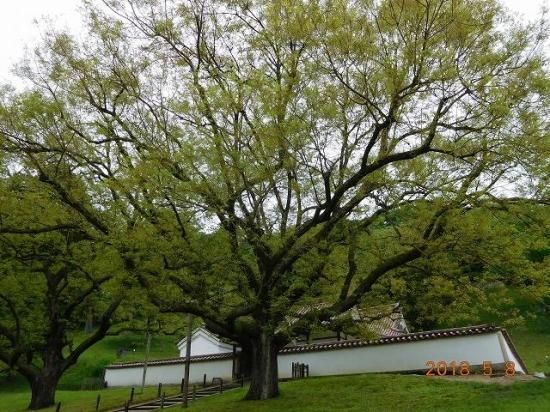
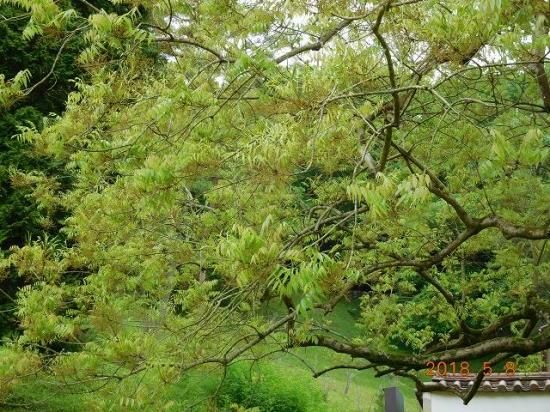

真正双子葉植物Eudicots>中核真正双子葉植物Core Eudicots>バラ類 Rosids>アオイ群 Malvids
ムクロジ目 Sapindales
ウルシ科 Anacardiaceae カイノキ属 Pistacia
別名:ランシンボク(爛心木)、トネリバハゼノキ
孔子木(孔子の木) 楷書の語源の樹
利用:観賞用 庭園木
中国三東省曲阜の孔子廟に植えられた木として有名。
孔子の死後、弟子の子貢は師の墓前に楷の樹を植えたと伝えられる。
楷の樹は葉や枝が整然と付き、書道の楷書の語源となった木といわれ、上下秩序を尊ぶ儒教の教えにふさわしかったのだろう。儒学に傾倒していた徳川5代将軍 綱吉は湯島聖堂を創建し孔子を祭り朱子学を奨励した。
中国では殆ど全土に生育しているカイノキ(楷の木)だが、わが国には大正4年に林学博士白澤保美氏が山東省曲阜の孔子墓所を訪れたさい、墓上に落ちていた種子を持ち帰り苗木に育て植えたのが最初。同時に儒学に所縁の各地、足利学校、金沢文庫、岡山の閑谷学校などに苗木が分与された。
ここ閑谷学校の楷の樹は樹高15〜17mに達し、実に堂々とした巨木に育っている。2本対に植えられ、ウルシ科であることから秋の紅葉は見事で、2本のうちの1本は赤く、もう1本は黄色に色づくという。孔子と楷とは離すことができないものとなっている。湯島聖堂のカイ(楷)の木と共に閑谷学校のカイ(楷)の木も曲阜の孔子の墓所の樹の子孫に当る由緒ある木だ。
外観はハゼノキに似ている。花はつぼみ時は赤く果実は紫がかった藍黒色に熟す。(ハセノキの花は黄緑色、果実は黒褐色)
高さ20〜25mにも成る。葉は偶数または奇数羽状複葉。小葉は5〜9対。4月頃葉脇から円錐花序を出し花を咲かせる。蕾は赤色をしているが咲くと淡い黄色になる。閑谷学校の楷ノ木も 枝先に円錐花序の様子が見えるが、4月頃開花のためすでに花は終わっていた。
岡山 旧閑谷学校 (きゅうしずたにがっこう)
江戸時代前期、寛文10年(1670年)岡山藩主 池田光政公が創建した藩立の学校だが、武士の子弟のみならず、ひろく庶民の子弟のために門戸を開いた。現存する世界で最古の庶民のための学校。備前焼瓦で葺かれた学問所、講堂は国宝に指定されている。
東京 湯島聖堂
徳川五代将軍 綱吉は元禄3年(1690)湯島(現在文京区湯島)に聖堂を創建し儒学の振興に努めた。これが湯島聖堂の始まり。後、幕府直轄学校として、「昌平坂学問所(通称『昌平校』)」となり儒学中心の学校として明治維新まで続いた。現在は国の史跡に指定されている。
PHoto:湯島聖堂 大成殿
参考文献
・朝日百科 世界の植物 (朝日新聞社)
・植物分類表 大場秀章 編著 (アボック社)
・日本の樹木 (山と渓谷社)
・湯島聖堂 楷樹の由来 案内板
PHoto:東京 湯島聖堂の楷樹の幹から芽生えた枝葉
整然とした羽状複葉の様子が分る