科目別の一覧
- 全ての植物
- サルノコシカケ科
- サルオガセ科
- ヒカゲノカズラ科
- トクサ科
- ウラボシ科
- ソテツ科
- イチョウ科
- マオウ科
- マツ科
- イチイ科
- ヒノキ科
- スイレン科
- ハゴロモモ科
- マツブサ科
- ドクダミ科
- コショウ科
- ウマノスズクサ科
- モクレン科
- バンレイシ科
- クスノキ科
- ショウブ科
- サトイモ科
- オモダカ科
- ヤマノイモ科
- ビャクブ科
- パナマソウ科
- シュロソウ科
- シオデ科
- ユリ科
- イヌサフラン科
- ラン科
- アヤメ科
- ツルボラン科
- ワスレグサ科
- ヒガンバナ科
- キジカクシ科
- ヤシ科
- ミクリ科
- ガマ科
- イネ科
- ツユクサ科
- バショウ科
- ショウガ科
- アケビ科
- ツヅラフジ科
- メギ科
- キンポウゲ科
- ケシ科
- ハス科
- タデ科
- ナデシコ科
- ヒユ科
- ツルムラサキ科
- ビャクダン科
- ボタン科
- ユズリハ科
- ユキノシタ科
- ブドウ科
- フウロウソウ科
- ミソハギ科
- アカバナ科
- フトモモ科
- ハマビシ科
- ニシキギ科
- ヤナギ科
- トケイソウ科
- トウダイグサ科
- オトギリソウ科
- ヒルギ科
- アマ科
- キントラノオ科
- カタバミ科
- マメ科
- ヒメハギ科
- バラ科
- グミ科
- クロウメモドキ科
- アサ科
- クワ科
- イラクサ科
- ウリ科
- ブナ科
- ヤマモモ科
- カバノキ科
- クルミ科
- パパイア科
- アブラナ科
- アオイ科
- ジンチョウゲ科
- ムクロジ科
- ウルシ科
- センダン科
- ミカン科
- ミズキ科
- アジサイ科
- ツバキ科
- カキノキ科
- サクラソウ科
- マタタビ科
- リョウブ科
- ツツジ科
- トチュウ科
- アオキ科
- ムラサキ科
- アカネ科
- リンドウ科
- キョウチクトウ科
- ナス科
- ヒルガオ科
- モクセイ科
- イワタバコ科
- キツネノマゴ科
- ゴマ科
- クマツヅラ科
- ノウゼンカズラ科
- シソ科
- ハマウツボ科
- オオバコ科
- ハナイカダ科
- モチノキ科
- ウコギ科
- セリ科
- トベラ科
- レンプクソウ科
- スイカズラ科
- キキョウ科
- ミツガシワ科
- キク科


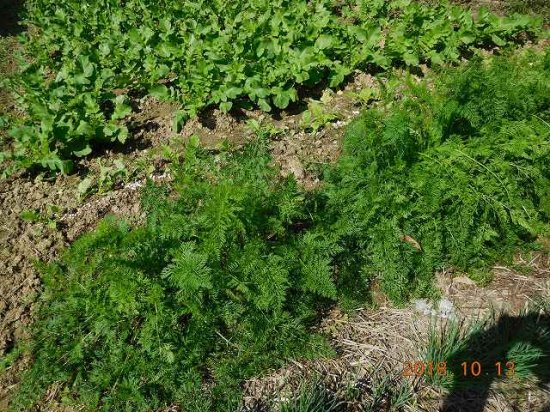
真正双子葉植物Eudicots>中核真正双子葉植物Core Eudicots>キク類Asterids>
キキョウ群Campanulids
セリ目Apiales
セリ科Umbelliferae(Apiaceae)ニンジンDaucus
栄養豊かな健康野菜
利用部分 :根 葉
利用 :食用
名前の由来 :根の形が先に渡来していた薬用の”チョウセンニンジン””の根に似ていたのと、葉の形
がセリの葉に似ていたので、当初は区別し”セリニンジン”の名で呼ばれていたのが、
野菜としての需要が定着化、いつしかセリが取れニンジンと言えば野菜のニンジンを
指すようになった。
ニンジンにはヨーロッパ系と東洋系の2つ系統がある。
原産地はアフガニスタン。トルコで野生種と交雑し12世紀頃ユ―ロッパに伝わったと推測される。
紫色、黄色の長根種が普及したが、橙色種がオランダで育成されると、18世紀以降はフランスやアメリカでは橙色短根種が主に育種され、発展しこれが今日のニンジンのヨーロッパ系の基本になっている。
東方へは原産国からシルクロードを経て、元の時代の中国華北に伝わり東洋系として発展した。
日本へは17世紀までには、東洋系長根形が伝わり、後ヨーロッパ系も伝わった。戦前までは東洋系赤長根種が主体であったが、現在は労力が少なくて済む短根のヨーロッパ系が主体になり、東洋系はキントキ(金時)ニンジン以外は栽培されなくなった。
ニンジンの花を観る機会はあまりないが初夏、花茎を伸ばし先端の複合散形花序に小さな白い5弁の花を咲かせる。葉は羽状複葉で2〜3回裂け、小葉は細長い卵型。ニンジンは根を主に食べるが、若葉も食用になる。ビタミンCやビタミンK、カルシウムを含んでいる。葉が入手できれば利用したい。
ニンジンの根は赤橙色をしている。この橙色素は”ニンジンの色”という語源からカロテンと名づけられた。赤色はリコピンで、ともに抗酸化作用があり体内の活性酸素の働きを抑制してくれ、動脈硬化や老化防止に役立ってくれる。カロテンにはαとβがあるがβカロテンは体内でビタミンAに変換される。
皮膚の粘膜保護、免疫力強化、暗闇での視力強化などの作用がある。
その他カリウム、食物繊維も多い。糖分も豊富に含み、栄養豊かで消化吸収もよく血行も盛んにすることから、病気で体力の低下した人の食べ物としても最適な野菜。調理方法も生でも、煮ても、油と共に炒めてもよく、いろいろの料理に幅広く利用できる。
ニンジンの花 5弁の白い花
参考文献
・朝日百科 世界の植物(朝日新聞社)
・生薬単 原島広至著(株式会社エヌ・ティ・エス)
・食材図典(小学館)
・食材事典 廣田孝子監修(学研)