����Ȳֵ��ԤΥۡ���ڡ���
| ̾������õ�� | ���� | ���� | ���� | ���� | �ʹ� | �Ϲ� | �� | ��� | ��� | ��� | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���Ӥ���õ�� | ������ | ������ʪ | �������������� | ̱���������� | �ʎ��̎ގ����̎ߎ؎Ҏݎ� | ����������� | ���Ѥ��Ϲ��� | ���������� | ���� | �վ��ѡ�����¾ |
�����̤ΰ���
- ���Ƥο�ʪ
- �������������
- ���륪������
- �ҥ����Υ������
- �ȥ�����
- ����ܥ���
- ���ƥIJ�
- �����祦��
- �ޥ�����
- �ޥIJ�
- ��������
- �ҥΥ���
- ��������
- �ϥ�������
- �ޥĥ֥���
- �ɥ����߲�
- �����祦��
- ���ޥΥ���������
- �⥯����
- �Х�쥤����
- ��������
- ���祦�ֲ�
- ���ȥ����
- ���������
- ��ޥΥ����
- �ӥ㥯�ֲ�
- �ѥʥޥ�����
- �����������
- �����Dz�
- ����
- ���̥��ե���
- ����
- ������
- �ĥ�ܥ���
- �凉�쥰����
- �ҥ���Хʲ�
- ������������
- �䥷��
- �ߥ����
- ����
- ���Ͳ�
- �ĥ楯����
- �Х��祦��
- ���祦����
- �����Ӳ�
- �ĥť�ե���
- ���
- ����ݥ�����
- ������
- �ϥ���
- ���Dz�
- �ʥǥ�����
- �ҥ��
- �ĥ��饵����
- �ӥ㥯�����
- �ܥ����
- �楺��ϲ�
- �業�Υ�����
- �֥ɥ���
- �ե�����������
- �ߥ��ϥ���
- �����Хʲ�
- �եȥ���
- �ϥޥӥ���
- �˥�������
- ��ʥ���
- �ȥ���������
- �ȥ�����������
- ���ȥ������
- �ҥ륮��
- ����
- ����ȥ�Υ���
- �����Х߲�
- �ޥ��
- �ҥ�ϥ���
- ���
- ���߲�
- ���ێ��ҎӎĎގ���
- ������
- �����
- ���饯����
- �����
- �֥ʲ�
- ��ޥ���
- ���ХΥ���
- ����߲�
- �ѥѥ�����
- ���֥�ʲ�
- ��������
- ������祦����
- �९������
- ���륷��
- ��������
- �ߥ����
- �ߥ�����
- ����������
- �ĥХ���
- ��������
- �����饽����
- �ޥ����Ӳ�
- ��祦�ֲ�
- �ĥĥ���
- �ȥ��奦��
- ��������
- ��饵����
- �����Ͳ�
- ���ɥ���
- ��������������
- �ʥ���
- �ҥ륬����
- �⥯������
- ���勵�Х���
- ���ĥͥΥޥ���
- ����
- ���ޥĥť��
- �Ɏ����ގݎ����ގײ�
- ������
- �ϥޥ��ĥܲ�
- ��������
- �ϥʥ�������
- �������
- ��������
- �����
- �ȥ٥��
- ���ץ�������
- �����������
- �����祦��
- �ߥĥ������
- ������


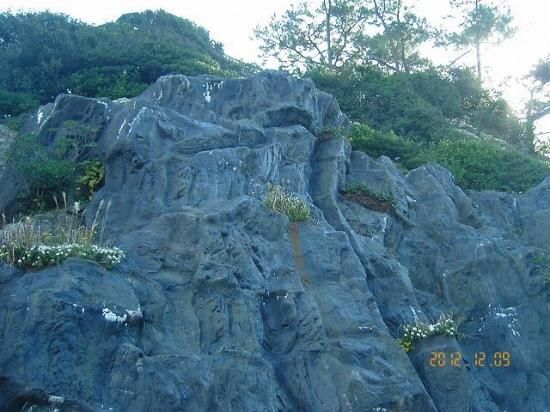
�����л��տ�ʪEudicots����˿����л��տ�ʪCore Eudicots�䥭����Asterids
�䥭���祦��Campanulids
����������Asterales
��������������Asteraceae������°Chrysanthemum��
������ʬ��������
�������������Ѿ���
̾����ͳ������������Ϻ��Τ�����Τθζ����θ��������ն��ϩ˵�˺餤�Ƥ���ΤĤ���
�������������������Ƥ�����˰��ߥΥ�������̿̾��
ʼ�˸��������ܽ��������ⳤ���彣�ʤɤ���ʿ��¦��γ��ߤ仳��˼����������ܤθ�ͭ����������ʤɤˤϼ������ʤ������ߤγ�����̤ʤɡ�Ĭ������������ʴĶ��˼������Ƥ��롣ȯ���Ԥ����ܤο�ʪ�ؤ���ȸ�������������Ϻ��Ρ�
1884ǯ������17ǯ����Τθζ������ߤϹ��Τ��龾���ؤΥХ�ƻ�˺餤�Ƥ���֤�Ѥ�̿̾������Ϻ��ݵƤ����Ĥȹͤ��Ƥ����������ݤεƤȤ��̼�����ܤθ�ͭ��Ǥ��뤳�Ȥ�ʬ����japonica��̾���դ���
���θ塢��Τ�ɱϩ�������ˬ�줿�ݡ��Υ��������緲���ȯ�����ز��ȯɽ����ʤɤ������Ȥ�ͭ̾�ˤʤꡢ�����˰���ʼ�˸��ϥΥ������β֡����֤˻��ꤷ�Ƥ��롣
�Υ�������¿ǯ����ϲ��ԤФ������롣�Ԥξ����Ǥ褯�ޤ�ʬ��������ĺ�����֤�1�Ĥ��ĺ餫���롣�֤Ӥ��������֤ϣ����������������濴�β����������֤�¿�����礷��Ⱦ�ߵ�ˤʤ롣������ʲ֤Ӥ�ˤ��ä������������Ǥ��������ʲ֤����褯�����֤˥�楦�Υ��������뤬���Υ������ϳ��ߤ˼�������֤ʤΤ��դ�ʬ�����դ��ڤ���ߤ�¿�������Ͽ�ʿ�ˤʤäƤ���ΤǸ�ʬ�����롣����奦�Υ��������դ����εǾ�˻�����꤬���뤬���Υ������Ϥ��ʤ��ΤǶ��̤Ǥ��롣���Ѥˤ���벫�����֤Υ��ޥ����Ȱۤʤ����ѤˤϤ���ʤ�����ͳ��ʤ��������֤Ǥ⤢�ꡢ�Τ�夲����
����ʸ��
������ī��ɴ�ʡ������ο�ʪ����ī����ʹ�ҡ�
�����������̾�������ߡ��ⶶ��ͺ������ʻ��ȷ�ë�ҡ�
���������ܤ�������ʪ�����ܭ�����ʿ�ҡ�
��������ʪʬ��ɽ����콨�ϡ��������ʥ��ܥå��ҡ�